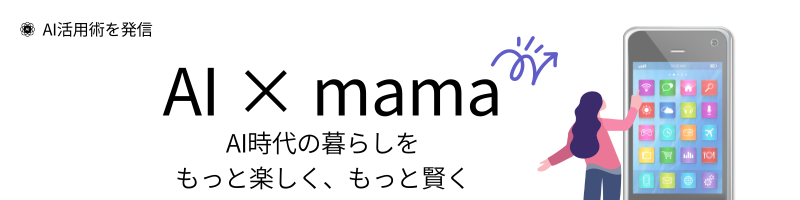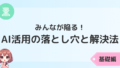びっくりしたニュースがあったので、今日はそのことをシェアしますね。
なんと、AIで作った”実在しない女性”のわいせつ画像を売っていた人たちが逮捕されたんです。
「えっ!?実在する人が写っているわけじゃないのに、どうして逮捕なの?」と疑問に思いませんか?
私も「え、それって法律違反になるの?」と驚いたので、詳しく調べてみました!
AIが作った”わいせつ画像”が売買されていた事件
報道によると、逮捕されたのは20代〜50代の4人。
AIを使って生成した”裸の女性”の画像をポスターにして、オークションサイトで販売していたそうです。
特筆すべきは、これらの画像に写っている女性は実在しない人だということ。
ネット上の画像を学習させたAIに「特定のポーズをとる」などと指示して、わいせつな画像を作成していたとのこと。
1年間で1000万円以上も売り上げた人もいたようです。そこまで稼げてしまう市場があることにも驚きですね。
実在しない人物の画像なのに、なぜ違法とされるのか
ここが一番疑問に感じるポイントだと思います。
実は、日本の刑法第175条では“わいせつな内容”そのものが規制対象なのです。
つまり、実在する人物が写っているかどうかではなく、その表現内容がわいせつと判断されれば法律違反となります。
過去にもアニメやマンガ、イラストが”わいせつ物頒布罪”で摘発された事例があります。
したがって、「AIで生成した架空の人物だからセーフ」という考えは通用しないということです。
技術の進化と社会的な課題
「実在する人を傷つけるわけではないのだから問題ないのでは?」と感じる方もいるかもしれません。
しかし、こうした画像が広く流通することで、性的対象としての女性像が強化されたり、青少年への悪影響が懸念されたりする問題もあります。
技術の発展スピードに、法整備や社会的なコンセンサスが追いついていない部分があるのは確かでしょう。
副業・収入源としても要注意
AIで画像を生成して販売することは、技術的には比較的容易になっています。「手軽な副業として試してみようかな」と考える方もいるかもしれませんが、内容によっては今回のように法律に抵触する可能性があることを認識しておく必要があります。
特に副業やクリエイター活動に興味のある方には、知っておいていただきたい重要な情報です。
まとめ:創作の自由と責任のバランス
AIは創作の可能性を大きく広げる素晴らしいツールです。
しかし「技術的に作成可能」というだけでなく、法的・倫理的に問題ないかどうかを常に意識することが重要になってきます。
これからもAI技術はさらに進化し、私たちの生活により深く浸透していくでしょう。
だからこそ、私たち一人ひとりが知識と倫理観を持ち、適切に活用していきたいものですね。